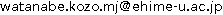-
Salinity tolerance in resting cysts of colpodid ciliates: Comparative transcriptomics analysis and chemical analysis of cyst walls to investigate their tolerance capability(コルポダの静止シストにおける塩分耐性: 比較トランスクリプトミクス解析とシスト壁の化学分析による耐性の検討)
査読
国際共著
国際誌
Saito, R., H. Yamanobe, K. Yabuki, T. Suzuki, T. Saito, S. Hakozaki, M. Wanner, R. Koizumi, T. Sakai, M. Gamboa, T. Tanaka, A. Ono, H. T. Nguyen, Y. Saito, T. Aoyama, K. Kojima, F. Suizu, K. Watanabe, Y. Sogame
Current Research in Microbial Sciences
, in press
2025年5月
-
Heterogeneous bacterial communities in gills and intestine of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and in water and sediments of aquacultureponds in Bangladesh (バングラデシュにおけるナイルティラピアの鰓と腸、養殖池の水と堆積物における不均一な細菌群集)
査読
国際共著
国際誌
Hossain, A, M. A.Zahid, S. K. Sanyal, M. I.-M. Haque, M. H.-A. Mamun, S. C. Mandal, K. Watanabe
Aquaculture and Fisheries
in press
2025年4月
-
Distribution pattern and diversity of Borrelia spp. detected from ticks in Niigata Prefecture, Japan(新潟県におけるマダニから検出されたボレリア属菌の分布パターンと多様性)
査読
Sato, M. O., S. Ikeda, M. Sato, R. Arai, J. Aoki, K. Watanabe, C. Hirokawa, K. Watanabe, M. A. F. Regilme, T. Tamura
BMC Research Notes
, in press
2025年4月
-
Occurrence, Risks, and Mitigation of Antibiotic Pollution in Bangladeshi Aquaculture Systems(バングラデシュの水産養殖システムにおける抗生物質汚染の発生、リスク、緩和策)
査読
国際共著
国際誌
Salma, U., Hossain, A., Shafiujjaman, Md, Nishimuraa, Y., Tokumura, M., Tanuoe, R., Kunisue, T., Watanabe, K., Raknuzzaman, M., Noro, K., Amagai, T., Makino, M.
Environmental Chemistry and Ecotoxicology
7
351
-
363
2025年3月
-
Occurrence, seasonal variation, and environmental risk of multiclass antibiotics in the urban surface water of the Buriganga River, Bangladesh(バングラデシュ・ブリガンガ川の都市表層水におけるマルチクラス抗生物質の存在、季節変動および環境リスク)
査読
国際共著
国際誌
Umma Salma, Yuri Nishimura, Masahiro Tokumura, Anwar Hossain, Kozo Watanabe, Kazushi Noro, Mohammad Raknuzzaman, Takashi Amagai, Masakazu Makino
Chemosphere
370
143956
2025年2月
-
Cross-taxa assessment of species diversity and phylogenetic structure of benthic communities in a dam-impacted river undergoing habitat restoration (生息場再生中のダム影響河川における底生生物群集の種多様性と系統構造のクロスタクサ評価)
査読
国際共著
国際誌
Joeselle Serrana, Bin Li, Kozo Watanabe
Science of the Total Environment
958
177886
2025年1月
-
Effects of water matrices on the removal of oxytetracycline antibiotic and total organic carbon (TOC) using four different oxidation processes (4つの異なる酸化プロセスを用いたオキシテトラサイクリン抗生物質と全有機炭素(TOC)の除去に対する水マトリックスの影響)
査読
国際共著
国際誌
Anwar Hossain, Yuri Nishimura, Umma Salma, Masahiro Tokumura, Takahiro Nishino, Mohammad Raknuzzaman, Kazushi Noro, Kozo Watanabe, Takashi Amagai, Masakazu Makino
Results in Engineering
24
103183
-
103183
2024年12月
-
Hybrid Machine Learning Approach to Zero-Inflated Data Improves Accuracy of Dengue Prediction(ゼロが多いデータに対するハイブリッド機械学習アプローチによりデング熱予測の精度が向上)
査読
国際共著
国際誌
Micanaldo Ernesto Francisco, Thaddeus M. Carvajal, Kozo Watanabe
PLOS Neglected Tropical Diseases
18
(
10
)
e0012599
-
e0012599
2024年10月
-
Environmental and Human Health Risk of Heavy Metals in Freshwater and Brackish Water Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Aquaculture (淡水・汽水ナイルティラピア養殖における重金属の環境・健康リスク)
査読
国際共著
国際誌
Md. Shafiujjaman, S. C. Mandal, M. Moniruzzaman, M. H.-A.-Mamun, M. A. A .Sheikh, K. Watanabe, A. Hossain
Environmental Geochemistry and Health
46
477
2024年10月
-
Natural Compound-Induced Downregulation of Antimicrobial Resistance and Biofilm-Linked Genes in Wastewater Aeromonas species(排水中のアエロモナス属細菌における天然化合物誘導による抗菌薬耐性およびバイオフィルム関連遺伝子の発現抑制
査読
国際共著
国際誌
Khristina G, Judan Cruz, Okamoto Takumi, Kenneth A. Bongulto, Emmanuel E. Gandalera, Ngure Kagia, Kozo Watanabe
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology
14
1456700
2024年10月
-
Response of wild aquatic insect communities to thermal variation through comparative landscape transcriptomics(比較景観トランスクリプトミクスによる水生昆虫群集の温度変化への応答)
査読
国際共著
Maribet Gamboa, Yusuke Gotoh, Arnelyn Doloiras‐Laraño, Kozo Watanabe
Archives of Insect Biochemistry and Physiology
116
(
4
)
e22137
2024年8月
-
α,β-trehalose, an intracellular substance in resting cyst of colpodid ciliates as a key to environmental tolerances(α,β-トレハロース、環境耐性の鍵となるコルポディティ繊毛虫の休眠シストにおける細胞内物質)
査読
国際誌
Yoichiro Sogame, Makoto Ogata, Shuntaro Hakozaki, Yuta Saito, Tomohiro Suzuki, Ryota Saito, Futoshi Suizu, Kozo Watanabe
Biochemical and Biophysical Research Communications
716
149971
2024年7月
-
Innovative house structures for malaria vector control in Nampula district, Mozambique: Assessing mosquito entry prevention, indoor comfort and community acceptance (モザンビークのナンプラにおけるマラリア媒介蚊対策のための革新的な家屋構造: 蚊の侵入防止、室内の快適性、地域住民の受容性の評価)
査読
国際共著
国際誌
Francisco, M. E, K. Watanabe
Frontiers in Public Health
12
1404493
2024年6月
-
Fine-scale adaptive divergence and population genetic structure of Aedes aegypti in Metropolitan Manila, Philippines(フィリピン・マニラ首都圏におけるネッタイシマカの微細空間スケールの適応分散と集団遺伝構造)
査読
国際共著
国際誌
Muharromah, A. F, T. M. Carvajal, M. A. F. Regilme, K. Watanabe
Parasites & Vector
17
233
2024年5月
-
Detection and quantification of natural Wolbachia in Aedes aegypti in Metropolitan Manila, Philippines (フィリピン・マニラ首都圏におけるネッタイシマカに自然感染したボルバキアの検出と定量化)
査読
国際誌
Jerica Isabel L. Reyes, Takahiro Suzuki, Yasutsugu Suzuki, Kozo Watanabe
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology
14
1360438
2024年3月
-
Genetic structure and Rickettsia infection rates in Ixodes ovatus and Haemaphysalis flava ticks across different altitudes(標高勾配に沿ったヤマトマダニ集団とキチマダニ集団の遺伝構造とリケッチア感染率)
査読
国際誌
Maria Angenica, F. Regilme, Megumi Sato, Tsutomu Tamura, Reiko Arai, Marcello Otake Sato, Sumire Ikeda, Kozo Watanabe
PLOS ONE
19
(
3
)
e0298656
2024年3月
-
Potential Way to Develop Dengue Virus Detection in Aedes Larvae as an Alternative for Dengue Active Surveillance: A Literature Review (デング熱アクティブサーベイランスの代替法としてネッタイシマカ幼虫からのデングウイルス検出法を開発する可能性: レビュー)
査読
国際共著
国際誌
Yenny Rachmawati, Savira Ekawardhani, Nisa Fauziah, Lia Faridah, Kozo Watanabe
Tropical Medicine and Infectious Disease
9
(
3
)
60
2024年3月
-
In vitro characterization of cell-fusing agent virus DNA forms in Aedes aegypti mosquitoes (ネッタイシマカにおける細胞融合型ウイルスDNAの特性のin vitro解析)
査読
Mohammad Mosleh Uddin, Yasutsugu Suzuki, Jerica Isabel L. Reyes, Kozo Watanabe
Virology
591
109982
2024年3月
-
Wastewater-based reproduction numbers and projections of COVID-19 cases in multiple cities in Japan, 2022(2022年の日本の複数都市における下水ベースの再生産数とCOVID-19感染者の予測)
査読
国際共著
国際誌
Shogo Miyazawa, Ting Sam Wong, Genta Ito, Ryo Iwamoto, Kozo Watanabe, Michiel van Boven, Jacco Wallinga, Fuminari Miura
Eurosurveillance
29
(
8
)
2300277
2024年2月
-
No detectable fitness cost of infection by cell-fusing agent virus in <i>Aedes aegypti</i> mosquitoes (ネッタイシマカの細胞融合型ウイルス感染へのフィットネスコストは検出されない)
査読
国際共著
国際誌
Yasutsugu Suzuki, Takahiro Suzuki, Fuminari Miura, Jerica Isabel L. Reyes, Irish Coleen A. Asin, Wataru Mitsunari, Mohammad Mosleh Uddin, Yu Sekii, Kozo Watanabe
Royal Society Open Science
11
(
1
)
231373
2024年1月
-
Recommendations of key elements within an integrated monitoring framework of antimicrobial resistance for Asian countries(アジア諸国のための抗菌薬耐性に関する統合モニタリングの枠組みにおける重要な要素の提言)
査読
国際共著
国際誌
Ryo Honda, Manish Kumar, Mardalisa, Rongxuan Wang, Muhammad Adnan Sabar, Tushara Chaminda, Kwanrawee Sirikanchana, Prasert Makkeaw, Sulfikar, Feng Ju, Guangming Jiang, Bing Li, Chart Chiemchaisri, Ryota Gomi, Mohan Amarasiri, Henrietta Venter, Masateru Nishiyama, Toru Watanabe, Masaru Ihara, Ikuro Kasuga, Kozo Watanabe, Satoru Suzuki
Environmental Science & Technology Letters
11
(
1
)
5
-
8
2024年1月
-
Arbovirus Detection of Adult Female Aedes aegypti for Dengue Surveillance: a Cohort Study in Bandung City, Indonesia (デング熱調査のためのネッタイシマ雌成虫のアルボウイルス検出:インドネシア・バンドン市におけるコホート研究)
査読
国際共著
国際誌
Faridah, L, S. Ekawardhani, N. Fauziah, I. D. Djati, R. E. Putra, K. Watanabe
Global Medical and Health Communication
11
(
3
)
225
-
233
2023年12月
-
The short-term influences of flow alteration on microbial community structure and putative metabolic functions in gravel bar hyporheic zones (砂州河床間隙水域における微生物群集構造と推定される代謝機能に及ぼす流れの変化の短期的影響)
査読
国際誌
Arnelyn D. Doloiras-Laraño, Joeselle M. Serrana, Shinji Takahashi, Yasuhiro Takemon, Kozo Watanabe
Frontiers in Environmental Science
11
1205561
2023年12月
-
Genome-wide detection of Wolbachia in natural Aedes aegypti populations using ddRAD-Seq (ddRAD-Seqを用いたネッタイシマカ自然集団におけるボルバキアのゲノムワイド検出)
査読
国際誌
Muharromah, A. F, J. Reyes, N. Kagia, K. Watanabe
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology
13
1252656
2023年12月
-
Marine bacteria harbor the sul4 sulfonamide-resistance gene without mobile genetic elements (スルホンアミド耐性遺伝子sul4を海洋細菌が移動性遺伝要素を介さずに保有する)
査読
国際誌
Suzune Shindoh, Aya Kadoya, Reo Kanechi, Kozo Watanabe, Satoru Suzuki
Frontiers in Microbiology
14
1230548
2023年9月
-
Bacterial diversity and antibiotic-resistant genes associated with the different farming systems of black tiger shrimp (Penaeus monodon) in Bangladesh (バングラデシュにおけるブラックタイガーエビ(Penaeus monodon)の異なる養殖システムに関連する細菌多様性と抗生物質耐性遺伝子)
査読
国際共著
国際誌
Md. Zakariaa, S. K. Sanyalb, Md. I-M. Haquea, S. C. Mandala, K. Watanabe, A. Hossain
Aquaculture Research
2023
6255586
2023年8月
-
Haplotype-level metabarcoding of freshwater macroinvertebrate species: a prospective tool for population genetic analysis (淡水大型無脊椎動物のハプロタイプレベルのメタバーコーディング:集団遺伝学的解析のための有用なツール)
査読
国際誌
Joeselle M. Serrana, Kozo Watanabe
PLOS ONE
18
(
7
)
e0289056
-
e0289056
2023年7月
-
Contrasting adaptive genetic consequences of stream insects under changing climate(気候変動下における河川昆虫の適応的遺伝的多様性の対照的な変化)
査読
Kei Nukazawa, Ming-Chih Chiu, So Kazama, Kozo Watanabe
Science of The Total Environment
872
162258
-
162258
2023年5月
-
New records for the Western Balkans cranefly fauna (Diptera, Tipuloidea) with the description of a new Baeoura Alexander (Diptera, Limoniidae) (西バルカン半島のガガンボ(Diptera, Tipuloidea)の新たな記録と新しいBaeoura 属(Diptera, Limoniidae)の新記載)
査読
国際共著
国際誌
Levente-Péter Kolcsár, Micha Camiel d’Oliveira, Wolfram Graf, Clovis Quindroi, Kozo Watanabe, Marija Ivković
ZooKeys
1157
1
-
42
2023年3月
-
The first record of Chaoborus punctipennis (Say, 1823), an invasive phantom midge (Diptera, Chaoboridae), in Japan(外来種Chaoborus punctipennis(双翅目、ケヨソイカ科、フサカ属)の日本における初の生息記録)
査読
国際共著
国際誌
Jukka Salmela, Keita Kuroda, Kota Ishimaru, Kozo Watanabe, Levente-Péter Kolcsár
BioInvasions Records
12
(
1
)
124
-
135
2023年3月
-
Contribution to the knowledge of Cylindrotomidae, Pediciidae and Tipulidae (Diptera: Tipuloidea): first records of 86 species from various European countries(ガガンボ上科 (Diptera: Tipuloidea) のCylindrotomidae, Pediciidae, Tipulidae の知識への貢献:ヨーロッパ各国からの86種の初記録)
査読
国際共著
国際誌
Kolcsár L-P, Oosterbroek P, Olsen P. M, Paramonov N. M, Gavryushin D, Pilipenko V. E, Polevoi A. V, Eiroa E, Andersson M, Dufour C, Syratt M, Kurina O, Lindström M, Starý J, Lantsov V, Wiedeńska J, Pape T, Friman M, Peeters K, Gritsch W, Janević D, Salmela J, Viitanen E, Aristophanous M, Watanabe K
Diversity
15
(
3
)
336
2023年2月
-
Environmental effects, gene flow and genetic drift: Unequal influences on genetic structure across landscapes (環境を介して景観レベルの遺伝構造に及ぼす遺伝子流動と遺伝的浮動の重要性は不均等である)
査読
国際共著
国際誌
Ming‐Chih Chiu, Kei Nukazawa, Vincent H. Resh, Kozo Watanabe
Journal of Biogeography
50
(
2
)
352
-
364
2023年2月
-
Spatial and phylogenetic structure of Alpine stonefly assemblages across seven habitats using DNA-species (アルプスの7つの生息地に分布するカワゲラ群集のDNA種の空間系統構造)
査読
Maribet Gamboa, Joeselle Serrana, Yasuhiro Takemon, Michael T. Monaghan, Kozo Watanabe
Oecologia
201
(
2
)
513
-
524
2023年1月
-
Metabarcoding data of mitochondrial cytochrome c oxidase subunit 1 gene from bulk community of aquatic organisms collected from Nara Prefecture, Japan(奈良県の水生生物群集のミトコンドリアシトクロムサブユニット1遺伝子のメタバーコーディングデータ)
査読
国際誌
Kei Wakimura, Koji Inai, Kazumi Tanida, Kozo Watanabe, Mikio Kato
Data in Brief
45
108599
-
108599
2022年12月
-
Japanese species of Ormosia Rondani (Diptera, Limoniidae): revision of the subgenera Oreophila Lackschewitz and Parormosia Alexander (Ormosia Rondani (Diptera, Limoniidae) の日本産種:Oreophila Lackschewitz と Parormosia Alexander 亜属の改訂)
査読
国際誌
Daichi Kato, Kozo Watanabe, Levente-Péter Kolcsár
ZooKeys
1132
127
-
162
2022年11月
-
ダム上下流河川の生息場構造異質性が底生動物の群集構造へ及ぼす影響
査読
高橋真司, 竹門康弘, 大村達夫, 渡辺幸三
土木学会論文集G(環境)
78
(
7
)
III_115
-
III_123
2022年10月
-
Optimal validated multi-factorial climate change risk assessment for adaptation planning and evaluation of infectious disease: A Case Study of Dengue Hemorrhagic Fever in Indonesia (感染症の適応計画と評価のための最適な検証済み多因子気候変動リスク評価。インドネシアにおけるデング出血熱のケーススタディ)
査読
国際共著
国際誌
Lia Faridah, Djoko Santoso Abi Suroso, Muhammad Suhardjono Fitriyanto, Clarisa Dity Andari, Isnan Fauzi, Yonatan Kurniawan, Kozo Watanabe
Tropical Medicine and Infectious Disease
7
(
8
)
172
-
172
2022年8月
-
Knowledge, attitudes, and practices regarding tick-borne diseases among an at-risk population living in Niigata prefecture, Japan(新潟県在住者のダニ媒介感染症に関する知識・態度・実践)
査読
国際誌
Taichi Narita, Hansani Madushika Abeywickrama, Marcello Otake Sato, Kozo Watanabe, Reiko Arai, Tsutomu Tamura, Megumi Sato
PloS one
17
(
6
)
e0270411
2022年6月
-
Spatially Varying Trophic Effects of Reservoir-Derived Plankton on Stream Macroinvertebrates Among Heterogeneous Habitats Within Reaches (ダム湖由来プランクトンが河川大型無脊椎動物に与える栄養効果は河川内の異なる生息場間で空間的に変化する)
査読
国際誌
Shinji Takahashi, Yasuhiro Takemon, Tatsuo Omura, Kozo Watanabe
Hydrobiologia
849
(
11
)
2503
-
2520
2022年5月
-
Detection and phylogeny of Wolbachia in field-collected Aedes albopictus and Aedes aegypti from Manila City, Philippines(フィリピン・マニラ市から野外採集したネッタイシマカおよびヒトスジシマカにおけるボルバキアの検出と系統解析)
査読
国際誌
Maria Angenica, F. Regilme, Tatsuya Inukai, Kozo Watanabe
European Journal of Molecular & Clinical Medicine
9
(
3
)
3060
-
3073
2022年5月
-
Temporal Correlation between Urban Microclimate, Vector Mosquito Abundance, and Dengue Cases (都市の微気候、媒介蚊の生息数、デング感染者数の時間相関)
査読
国際共著
国際誌
Lia Faridah, Nisa Fauziah, Dwi Agustian, I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ramadhani Eka Putra, Savira Ekawardhani, Nurrachman Hidayath, Imam Damar Djati, Thaddeus M Carvajal, Wulan Mayasari, Fedri Ruluwedrata Rinawan, Kozo Watanabe
Journal of Medical Entomology
59
(
3
)
1008
-
1018
2022年5月
-
Implications of taxonomic and numerical resolution on DNA metabarcoding-based inference of benthic macroinvertebrate responses to river restoration(DNAメタバーコーディングによる自然再生の河川底生動物への反応推定における分類学的および数値的分解能の影響)
査読
国際誌
Joeselle M. Serrana, Bin Li, Tetsuya Sumi, Yasuhiro Takemon, Kozo Watanabe
Ecological Indicators
135
108508
-
108508
2022年2月
-
Life history and host plant assessment of the cacao mirid bug Helopeltis bakeri Poppius (Hemiptera: Miridae)(カカオカメムシHelopeltis bakeri Poppius(半翅目:アリ科)の生活史と寄主植物の評価)
査読
国際共著
国際誌
Joeselle M. Serrana, Leslie Ann C. Ormenita, Billy Joel M. Almarinez, Kozo Watanabe, Alberto T. Barrion, Divina M. Amalin
Phytoparasitica
50
(
1
)
1
-
12
2022年2月
-
Notes on the Taxonomic Status and Distribution of Some Cylindrotomidae (Tipuloidea, Diptera), with Emphasis on Japanese Species(日本産種に焦点を当てたいくつかのCylindrotomidae(ガガンボ上科、双翅目)の分類学的状態と分布に関する記録)
査読
国際共著
Levente-Péter Kolcsár, Nikolai Paramonov, Yume Imada, Daichi Kato, Maribet Gamboa, Dai Shinoka, Makoto Kato, Kozo Watanabe
ZooKeys
1083
(
1083
)
13
-
88
2022年1月
-
Sediment-associated Microbial Community Profiling: Sample Pre-processing through Sequential Membrane Filtration for 16s rDNA Amplicon Sequencing(堆積物中の微生物群集のプロファイリング:16srDNAアンプリコンシーケンシングのための順次的膜ろ過によるサンプル前処理)
査読
国際誌
Joeselle M. Serrana, Kozo Watanabe
BMC Microbiology
22
(
1
)
2022年1月
-
Loss of a larval generic character: an interesting and new description for Isoperla vevcianensis Ikonomov, 1980 (Plecoptera: Perlodidae) with updated adult characters(幼生期の特徴が失われたIsoperla vevcianensis Ikonomov, 1980(カワゲラ目、アミメカワゲラ科)の興味深い新種記載と成虫の特徴の更新)
査読
国際共著
国際誌
DÁVID MURÁNYI, TIBOR KOVÁCS, MARIBET GAMBOA, KOZO WATANABE
Zootaxa
5082
(
6
)
541
-
552
2021年12月
-
Profiling the Microbial Community Structure and Functional Diversity of a Dam-regulated River Undergoing Gravel Bar Restoration(ダム下流の砂州再生河川の微生物群集構造と機能的多様性のプロファイリング)
査読
国際誌
Joeselle M. Serrana, Bin Li, Tetsuya Sumi, Yasuhiro Takemon, Kozo Watanabe
Freshwater Biology
66
(
11
)
2170
-
2184
2021年11月
-
Dengue disease dynamics are modulated by the combined influences of precipitation and landscape: A machine learning approach(デング熱の疾病動態は降水量と景観の複合的な影響によって変調をきたす:機械学習によるアプローチ)
査読
国際共著
国際誌
Micanaldo Ernesto Francisco, Thaddeus M. Carvajal, Masahiro Ryo, Kei Nukazawa, Divina M. Amalin, Kozo Watanabe
Science of The Total Environment
792
148406
-
148406
2021年10月
-
Comparative population genetic structure of two ixodid tick species (Acari:Ixodidae) (Ixodes ovatus and Haemaphysalis flava) in Niigata prefecture, Japan(新潟県のマダニ2種(ヤマトマダニとキチマダニ)の集団遺伝構造の比較)
査読
国際共著
国際誌
Maria Angenica, F. Regilme, Megumi Sato, Tsutomu Tamura, Reiko Arai, Marcello Otake Sato, Sumire Ikeda, Maribet Gamboa, Michael T. Monaghan, Kozo Watanabe
Infection, Genetics and Evolution
94
104999
-
104999
2021年10月
-
Carotenoid Coloration and Coloration-Linked Gene Expression in Red Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Tissues (レッドナイルティラピア(Oreochromis niloticus)組織におけるカロテノイド色素と色素に関連した遺伝子発現)
査読
国際誌
Khristina G, Judan Cruz, Ervee P. Landingin, Maureen B. Gajeton, Somar Israel D. Fernando, Kozo Watanabe
BMC Veterinary Research
17
(
1
)
314
2021年9月
-
Next Generation of AMR Network(次世代の抗菌剤耐性ネットワーク)
査読
国際誌
Payumo, J. G, E. Alocilja, C. Boodoo, K. Luchini-Colbry, P. Ruegg, E. Mclamore, D. V. Gamboa, R. K. Briceno, A. Castaneda-Sabogal, K. Watanabe, M. J. Gordoncillo, D. Amalin, L. Fernando, N. Bhusal
Encyclopedia
1
(
3
)
871
-
892
2021年8月
-
Contribution to the knowledge of Limoniidae (Diptera: Tipuloidea): first records of 244 species from various European countries (双翅目(ガガンボ上科)の知識への貢献:ヨーロッパ諸国からの244種の最初の記録)
査読
国際共著
国際誌
Levente-Péter Kolcsár, Pjotr Oosterbroek, Dmitry Gavryushin, Kjell Magne Olsen, Nikolai Paramonov, Valentin Pilipenko, Jaroslav Starý, Alexei Polevoi, Vladimir Lantsov, Eulalia Eiroa, Michael Andersson, Jukka Salmela, Clovis Quindroit, Micha d'Oliveira, E. Geoffrey Hancock, Jorge Mederos, Pete Boardman, Esko Viitanen, Kozo Watanabe
Biodiversity Data Journal
9
e67085
2021年7月
-
Intracellular Interactions Between Arboviruses and Wolbachia in Aedes aegypti(ネッタイシマカにおけるアルボウイルスとボルバキアの細胞内相互作用)
査読
国際共著
国際誌
Jerica Isabel L. Reyes, Yasutsugu Suzuki, Thaddeus Carvajal, Maria Nilda M. Muñoz, Kozo Watanabe
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology
11
690087
2021年6月
-
Acute oral toxicity assessment of ethanolic extracts of Antidesma bunius (L.) Spreng fruits in mice(マウスを用いたスプレンギング果実Antisesma bunius(L.)のエタノール抽出物の急性経口毒性の評価)
査読
国際誌
Maria Nilda, M. Muñoz, Urdujah G. Alvarado, Jerica Isabel L. Reyes, Kozo Watanabe
Toxicology Reports
8
1289
-
1299
2021年6月
-
Spatial and temporal analysis of hospitalized dengue patients in Bandung: demographics and risk(バンドンにおけるデング熱の入院患者の時空間的分析:人口統計とリスク)
査読
国際誌
Lia Faridah, I. Gede, Nyoman Mindra, Ramadhani Eka Putra, Nisa Fauziah, Dwi Agustian, Yessika Adelwin Natalia, Kozo Watanabe
Tropical Medicine and Health
49
(
1
)
44
2021年5月
-
Candida albicans Biofilm Inhibition by Ethnobotanicals and Ethnobotanically-Synthesized Gold Nanoparticles(生物学的に合成された金ナノ粒子によるカンジダアルビカンスのバイオフィルム阻害)
査読
国際共著
国際誌
Khristina G, Judan Cruz, Eleonor D. Alfonso, Somar Israel D. Fernando, Kozo Watanabe
Frontiers in Microbiology
12
665113
2021年5月
-
Detailed Description and Illustration of Larva, Pupa, and Imago of Holorusia mikado (Westwood, 1876) (Diptera: Tipulidae) from Japan(ミカドガガンボ(Holorusia mikado(Westwood、1876))(双翅目:ガガンボ科)の幼虫、蛹、成虫の詳細な記載とイラストレーション)
査読
国際誌
Kolcsár, L-P, D. T, Nakamura, Kato, K. Watanabe
Biodiversity Data Journal
9
e58009
2021年5月
-
Diversity and distribution of ticks in Niigata prefecture, Japan (2016–2018): Changes since 1950(新潟県におけるマダニの多様性と分布(2016-2018年):1950年代からの変化)
査読
国際誌
Megumi Sato, Sumire Ikeda, Reiko Arai, Miwako Kato, Junko Aoki, Akiko Nishida, Kaori Watanabe, Chika Hirokawa, Kozo Watanabe, Maria Angenica, F. Regilme, Mami Sato, Marcello Otake Sato, Tsutomu Tamura
Ticks and Tick-borne Diseases
12
(
3
)
101683
-
101683
2021年5月
-
Erratum: Correction: Early Detection of Dengue Fever Outbreaks Using a Surveillance App (Mozzify): Cross-sectional Mixed Methods Usability Study (JMIR public health and surveillance (2021) 7 3 (e19034))
Von Ralph Dane Marquez Herbuela, Tomonori Karita, Thaddeus Marzo Carvajal, Howell Tsai Ho, John Michael Olea Lorena, Rachele Arce Regalado, Girly Dirilo Sobrepeña, Kozo Watanabe
JMIR public health and surveillance
7
(
4
)
e29795
2021年4月
-
Early Detection of Dengue Fever Outbreaks Using a Surveillance App (Mozzify): Cross-sectional Mixed Methods Usability Study(調査モバイルアプリ「モジファイ」を使ったデング熱流行の早期検出:複合的手法の横断的な有用性研究)
査読
国際共著
国際誌
Von Ralph, Dane Marquez Herbuela, Tomonori Karita, Thaddeus Marzo Carvajal, Howell Tsai Ho, John Michael Olea Lorena, Rachele Arce Regalado, Girly Dirilo Sobrepeña, Kozo Watanabe
JMIR Public Health and Surveillance
7
(
3
)
e19034
-
e19034
2021年3月
-
The influence of roads on the fine-scale population genetic structure of the dengue vector Aedes aegypti (Linnaeus)(デング熱媒介生物ネッタイシマカの微細空間スケールの集団遺伝構造に及ぼす道路の影響)
査読
国際共著
国際誌
Maria Angenica, F. Regilme, Thaddeus M. Carvajal, Ann–Christin Honnen, Divina M. Amalin, Kozo Watanabe
PLOS Neglected Tropical Diseases
15
(
2
)
e0009139
2021年2月
-
Spotted fever group rickettsiae (SFGR) detection in ticks following reported human case of Japanese spotted fever in Niigata Prefecture, Japan(新潟県における日本紅斑熱ヒト症例の発生後におけるダニに感染したリケッチアの追跡調査)
査読
Reiko Arai, Megumi Sato, Miwako Kato, Junko Aoki, Akiko Nishida, Kaori Watanabe, Chika Hirokawa, Sumire Ikeda, Kozo Watanabe, Maria Angenica, F. Regilme, Marcello Otake Sato, Tsutomu Tamura
Scientific Reports
11
(
1
)
2595
2021年1月
-
A Bioclimate-Based Maximum Entropy Model for Comperiella calauanica Barrion, Almarinez and Amalin (Hymenoptera: Encyrtidae) in the Philippines(生気候に基づくフィリピンの寄生バチComperiella calauanicaの最大エントロピーモデル)
査読
Billy Joel M. Almarinez, Mary Jane A. Fadri, Richard Lasina, Mary Angelique A. Tavera, Thaddeus M. Carvajal, Kozo Watanabe, Jesusa C. Legaspi, Divina M. Amalin
Insects
12
(
1
)
26
-
26
2021年1月
-
Wing geometry and genetic analyses reveal contrasting spatial structures between male and female Aedes aegypti (L.) (Diptera: Culicidae) populations in metropolitan Manila, Philippines(フィリピンのマニラ首都圏のネッタイシマカの翅形状および遺伝分析により雄雌間の対照的な空間集団構造が明らかになる)
査読
国際共著
国際誌
Thaddeus M. Carvajal, Divina M. Amalin, Kozo Watanabe
Infection, Genetics and Evolution
87
104676
-
104676
2021年1月
-
Underdiagnosis does not account for the decrease in dengue cases in Bandung, Indonesia(インドネシア・バンドンにおけるデング熱感染者数の低下は過小診断では説明されない)
査読
国際共著
国際誌
Faridah, L, S. Ekawardhani, H. L. Wiraswati, N. Fauziah, F. R. Rinawan, W. Mayasarid, K. Watanabe
Systematic Reviews in Pharmacy
12
(
1
)
1340
-
1342
2021年1月
-
Revision of Japanese species of Nipponomyia Alexander, 1924 (Diptera, Pediciidae)(日本産Nipponomyia属(双翅目、ガガンボ科)の種の再定義)
査読
Levente-Péter Kolcsár, Daichi Kato, Maribet Gamboa, Kozo Watanabe
ZooKeys
2020
(
1000
)
71
-
105
2020年12月
-
Branching networks can have opposing influences on genetic variation in riverine metapopulations(分岐ネットワークが河川のメタ集団の遺伝的多様性に及ぼす相反する影響を及ぼす)
査読
Ming‐Chih Chiu, Bin Li, Kei Nukazawa, Vincent H. Resh, Thaddeus Carvajal, Kozo Watanabe
Diversity and Distributions
26
(
12
)
1813
-
1824
2020年12月
-
Simulation modeling reveals the evolutionary role of landscape shape and species dispersal on genetic variation within a metapopulation(シミュレーションモデルが解明する景観の輪郭と種の移動分散がメタ個体群の遺伝的多様性に及ぼす進化的役割)
査読
Ming‐Chih Chiu, Kei Nukazawa, Thaddeus Carvajal, Vincent H. Resh, Bin Li, Kozo Watanabe
Ecography
43
(
12
)
1891
-
1901
2020年12月
-
Synopsis of the genus Ulomorpha Osten Sacken, 1869 (Diptera, Limoniidae) in Japan(日本のウルモルファ属(双翅目,ヒメガガンボ科)の概要)
査読
Daichi Kato, Kozo Watanabe, Levente-Péter Kolcsár
ZooKeys
2020
(
999
)
147
-
163
2020年11月
-
Surveillance of Dengue Virus in Individual Aedes aegypti Mosquitoes Collected Concurrently with Suspected Human Cases in Tarlac City, Philippines (フィリピン・ターラック市において感染が疑われる患者と同時に採取した蚊サンプルのデングウイルス個体ベース調査)
査読
国際誌
Jean Claude Balingi, Thaddeus M Carvajal, Mariko Saito-Obata, Maribet Gamboa, Amalea Dulcene Nicolasora, Ava Kristy Sy, Hitoshi Oshitani, Kozo Watanabe
Parasites & vectors
13
(
1
)
594
-
594
2020年11月
-
Biological Control: A Major Component of the Pest Management Program for the Invasive Coconut Scale Insect, Aspidiotus rigidus Reyne, in the Philippines(生物的防除によるフィリピンの侵略的ココヤシ寄生虫Aspidiotus rigidus Reyneの害虫管理プログラム)
査読
Billy Joel M. Almarinez, Alberto T. Barrion, Mario V. Navasero, Marcela M. Navasero, Bonifacio F. Cayabyab, Jose Santos, R. Carandang, Jesusa C. Legaspi, Kozo Watanabe, Divina M. Amalin
Insects
11
(
11
)
745
-
745
2020年10月
-
Remarkable anoxia tolerance by stoneflies from a floodplain aquifer(氾濫原帯水層のカワゲラが有する顕著な無酸素耐性)
査読
Rachel L. Malison, Bonnie K. Ellis, Amanda G. DelVecchia, Hailey Jacobson, Brian K. Hand, Gordon Luikart, H. Arthur Woods, Maribet Gamboa, Kozo Watanabe, Jack A. Stanford
Ecology
101
(
10
)
e03127
2020年10月
-
Spatial genetic structure of the invasive tree Robinia pseudoacacia to determine migration patterns to inform best practices for riparian restoration.(外来河畔樹ハリエンジュの空間遺伝構造は河岸再生に最適な移動パターンを決定する)
査読
国際誌
Sakiko Yaegashi, Tatsuo Omura, Kozo Watanabe
AoB PLANTS
12
(
5
)
plaa043
2020年10月
-
Remarkable Anoxia Tolerance by Stoneflies from a Floodplain Aquifer(氾濫原帯水層のカワゲラが有する顕著な無酸素耐性)
Rachel L. Malison, Bonnie K. Ellis, Amanda G. DelVecchia, Hailey Jacobson, Brian K. Hand, Gordon Luikart, H. Arthur Woods, Maribet Gamboa, Kozo Watanabe, Jack A. Stanford
The Bulletin of the Ecological Society of America
101
(
4
)
e01767
2020年10月
-
Quorum Sensing-Linked agrA Expression by Ethno-Synthesized Gold Nanoparticles in Tilapia Streptococcus agalactiae Biofilm Formation(ティラピアStreptococcus agalactiaeの生物膜構造における民族合成された金ナノ粒子によるクオラムセンシング関連agrA発現)
査読
Somar Israel D. Fernando, Khristina G. Judan Cruz, Kozo Watanabe
BioNanoScience
10
(
3
)
696
-
704
2020年9月
-
Machine-learning-based detection of adaptive divergence of the stream mayfly Ephemera strigata populations(機械学習による河川性カゲロウのモンカゲロウ個体群の適応放散の検出)
査読
国際誌
Bin Li, Sakiko Yaegashi, Thaddeus M. Carvajal, Maribet Gamboa, Ming Chih Chiu, Zongming Ren, Kozo Watanabe
Ecology and Evolution
10
(
13
)
6677
-
6687
2020年7月
-
Fine-scale population genetic structure of dengue mosquito vector, Aedes aegypti, in Metropolitan Manila, Philippines(フィリピン・マニラ首都圏におけるデング熱媒介蚊ネッタイシマカの微小空間スケールにおける集団遺伝構造)
査読
国際誌
Thaddeus M. Carvajal, Kohei Ogishi, Sakiko Yaegeshi, Lara Fides T. Hernandez, Katherine M. Viacrusis, Howell T. Ho, Divina M. Amalin, Kozo Watanabe
PLOS Neglected Tropical Diseases
14
(
5
)
e0008279
-
e0008279
2020年5月
-
A remarkable new genus and species of Nemourinae (Plecoptera, Nemouridae) from Sichuan, China, with systematic notes on the related genera(中国・四川省のオナシカワゲラ科の注目すべき新属と新種,関連する属との分類学的記載と共に)
査読
RaoRao Mo, Maribet Gamboa, Kozo Watanabe, GuoQuan Wang, WeiHai Li, Ding Yang, Dávid Murányi
PLOS ONE
15
(
3
)
e0229120
-
e0229120
2020年3月
-
Evaluation of health information system (HIS) in the surveillance of dengue in Indonesia: Lessons from case in Bandung, West Java(インドネシアのデング熱調査における健康情報システムの評価:インドネシア・西ジャワ州バンドンの事例から示された課題)
査読
国際誌
Lia Faridah, Fedri Ruluwedrata Rinawan, Nisa Fauziah, Wulan Mayasari, Angga Dwiartama, Kozo Watanabe
International Journal of Environmental Research and Public Health
17
(
5
)
2020年3月
-
An Integrated mHealth App for Dengue Reporting and Mapping, Health Communication, and Behavior Modification: Development and Assessment of (デング熱患者のレポート,マッピング,医療コミュニケーション,行動変容のための統合的モバイルヘルスアプリMozzify (モズィファイ)の開発と評価)
査読
国際共著
国際誌
Von Ralph, Dane Marquez Herbuela, Tomonori Karita, Micanaldo Ernesto Francisco, Kozo Watanabe
JMIR Formative Research
4
(
1
)
e16424
-
e16424
2020年1月
-
A new species of Protonemura Kempny, 1898 (Plecoptera: Nemouridae) from the Ishizuchi range, Shikoku, Japan(日本の四国・石鎚から見つかったユビオナシカワゲラ属の新種)
査読
国際誌
Dávid Murányi, Maribet Gamboa, Kozo Watanabe
Zootaxa
4718
(
1
)
57
-
66
2020年1月
-
Depressive and anxiety symptoms among pediatric in-patients with dengue fever: A case-control study(デング熱入院小児患者のうつ病と不安神経症:症例対照研究)
査読
国際共著
国際誌
Von Ralph, Dane M. Herbuela, Ferdinand, S. de Guzman, Girly D. Sobrepeña, Andrew Benedict, F. Claudio, Angelica Cecilia V. Tomas, Carmina M.Arriola, Delos Reyes, Rachele A. Regalado, Mariama M. Teodoro, Kozo Watanabe
International Journal of Environmental Research and Public Health
17
(
1
)
99
2020年1月
-
Knowledge, attitude, and practices regarding dengue fever among pediatric and adult in-patients in metro Manila, Philippines(フィリピン・マニラ首都圏におけるデング熱入院小児および成人患者のデング熱に関する知識・態度・実践)
査読
国際共著
国際誌
Von Ralph, Dane M. Herbuela, Ferdinand, S. de Guzman, Girly D. Sobrepeña, Andrew Benedict, F. Claudio, Angelica Cecilia V. Tomas, Carmina M.Arriola, Delos Reyes, Rachele A. Regalado, Mariama M. Teodoro, Kozo Watanabe
International Journal of Environmental Research and Public Health
16
(
23
)
4705
2019年12月
-
Unraveling the Genetic Structure of the Coconut Scale Insect Pest (Aspidiotus rigidus Reyne) Outbreak Populations in the Philippines.(フィリピンで拡大するココヤシ寄生虫Aspidiotus rigidus集団の遺伝構造の解明)
査読
国際誌
Joeselle M Serrana, Naoto Ishitani, Thaddeus M Carvajal, Billy Joel M Almarinez, Alberto T Barrion, Divina M Amalin, Kozo Watanabe
Insects
10
(
11
)
374
2019年10月
-
Detection of Wolbachia in field-collected Aedes aegypti mosquitoes in metropolitan Manila, Philippines(フィリピン・マニラ首都圏で野外採取された媒介蚊ネッタイシマカからのボルバキア検出)
査読
国際誌
Thaddeus M. Carvajal, Kazuki Hashimoto, Reza Kurniawan Harnandika, Divina M. Amalin, Kozo Watanabe
Parasites & Vectors
12
(
1
)
361
-
361
2019年7月
-
Is Rapid Dengue Test Necessary at Primary Health Centre? A Study In Bandung City(デング熱迅速検査は1次医療機関に必要なのか?バンドンの事例研究)
査読
Faridah, L, N. Fauziah, S Ekawardhani, Riyadi, K. Watanabe
Journal of Clinical and Diagnostic Research
13
(
7
)
DC20
-
DC23
2019年7月
-
Comparison of DNA metabarcoding and morphological identification for stream macroinvertebrate biodiversity assessment and monitoring(河川大型無脊椎動物の生物多様性評価におけるメタバーコーディングと形態学的種同定の比較)
査読
国際共著
国際誌
Joeselle M. Serrana, Yo Miyake, Maribet Gamboa, Kozo Watanabe
ECOLOGICAL INDICATORS
101
963
-
972
2019年6月
-
Genome-wide signatures of local adaptation among seven stoneflies species along a nationwide latitudinal gradient in Japan(日本の緯度勾配に沿った河川性カワゲラの局所的適応のゲノムワイドシグネチャー)
査読
国際誌
Maribet Gamboa, Kozo Watanabe
BMC Genomics
20
(
1
)
84
-
84
2019年1月
-
Molecular phylogeny and diversification timing of the Nemouridae family (Insecta, Plecoptera) in the Japanese Archipelago(日本列島のオナシカワゲラ科の分子系統と種多様化のタイミング)
査読
国際誌
Maribet Gamboa, David Muranyi, Shota Kanmori, Kozo Watanabe
PLoS ONE
14
(
1
)
e0210269
2019年1月
-
Ecological influence of sediment bypass tunnels on macroinvertebrates in dam-fragmented rivers by DNA metabarcoding(DNAメタバーコーディングによるダム分断河川に生息する大型無脊椎動物への排砂バイパストンネルの生態学的効果の評価)
査読
国際誌
Joeselle M. Serrana, Sakiko Yaegashi, Shunsuke Kondoh, Bin Li, Christopher T. Robinson, Kozo Watanabe
Scientific Reports
8
(
1
)
10185
-
10185
2018年12月
-
Detection and distribution of Wolbachia endobacteria in Culex quinquefasciatus populations (Diptera : Culicidae) from Metropolitan Manila, Philippines(フィリピン・マニラ首都圏に生息するネッタイイエカからの共生細菌ボルバキアの検出とその空間分布)
査読
国際共著
国際誌
Thaddeus Carvajal, Jayson Dale Capistrano, Kazuki Hashimoto, Kristin Joyce Go, Maria Angeline, Isabelle Cruz, Monique Johanne Lourdee Martinez, Vincent Stefano Tiopianco, Divina Amalin, Kozo Watanabe
Journal of Vector Borne Diseases
55
(
4
)
265
-
270
2018年12月
-
Using Google trends to examine the spatio-temporal incidence and behavioral patterns of dengue disease: A case study in metropolitan Manila, Philippines(グーグルトレンドを使ったデング熱罹患率と患者行動の時空間パターンの解析:フィリピン・メトロマニラのケーススタディー)
査読
国際共著
国際誌
Howell T. Ho, Thaddeus M. Carvajal, John Robert Bautista, Jayson Dale, R. Capistrano, Katherine M. Viacrusis, Lara Fides T. Hernandez, Kozo Watanabe
Tropical Medicine and Infectious Disease
3
(
4
)
118
2018年11月
-
マニラ首都圏におけるデング熱媒介蚊の産卵活動に関わる因子の時空間的分析
査読
糠澤桂, 西元竣哉, 鈴木祥広, 渡辺幸三
土木学会論文集G(環境)
Vol.74, No.5, pp.I_79-I_85,
(
No.5
)
I_79
-
I_85
2018年9月
-
Free-chlorine disinfection as a selection pressure on norovirus(ノロウイルスの選択圧としての遊離塩素による不活化)
査読
国際誌
Andri Taruna Rachmadi, Masaaki Kitajima, Kozo Watanabe, Sakiko Yaegashi, Joeselle Serrana, Arata Nakamura, Toyoko Nakagomi, Osamu Nakagomi, Kazuhiko
Applied and Environmental Microbiology
84
(
13
)
e00244-18
2018年7月
-
Machine learning methods reveal the temporal pattern of dengue incidence using meteorological factors in metropolitan Manila, Philippines(機械学習を用いたフィリピン・メトロマニラにおけるデング熱罹患率の時間変動パターンの気象因子に基づく解明)
査読
国際共著
国際誌
Thaddeus M. Carvajal, Katherine M. Viacrusis, Lara Fides T. Hernandez, Howell T. Ho, Divina M. Amalin, Kozo Watanabe
BMC Infectious Diseases
18
(
1
)
183
-
183
2018年4月
-
Macroinvertebrate Community in Subsurface-Flow Constructed Wetlands for Wastewater Treatment under High and Low Pollutant Stress in China(中国における高濃度および低濃度の汚水を処理する伏流水型人工湿地に生息する大型無脊椎動物群集)
査読
Bin Li, Yang Yang, Sai Wang, Ming Wang, Kozo Watanabe
Wetlands
38
(
2
)
391
-
399
2018年4月
-
Disinfection as a Selection Pressure on RNA Virus Evolution.(RNAウイルス進化における選択圧としての不活化)
査読
国際誌
Andri Taruna Rachmadi, Masaaki Kitajima, Kozo Watanabe, Satoshi Okabe, Daisuke Sano
Environmental science & technology
52
(
5
)
2434
-
2435
2018年3月
-
河川水中の環境DNAの次世代シーケンス解析を利用した水生昆虫の群集構造および生息個体数推定の可能性:従来型定量評価手法と比較して
査読
八重樫咲子, 細川大樹, 渡辺幸三
土木学会論文集G(環境)
73
(
7
)
III_139
-
III_147
2017年11月
-
Differences in protein expression among five species of stream stonefly (Plecoptera) along a latitudinal gradient in Japan.(日本の気候勾配に沿ったタンパク発現パターンの河川性カワゲラ5種の違い)
査読
国際誌
Maribet Gamboa, Maria Claret Tsuchiya, Suguru Matsumoto, Hisato Iwata, Kozo Watanabe
Archives of insect biochemistry and physiology
96
(
3
)
2017年11月
-
Comparative tests of the species-genetic diversity correlation at neutral and nonneutral loci in four species of stream insect.(河川水生昆虫4種の中立および選択性遺伝子座における種多様性と遺伝的多様性の相関に関する比較解析)
査読
国際共著
国際誌
Kozo Watanabe, Michael T Monaghan
Evolution; international journal of organic evolution
71
(
7
)
1755
-
1764
2017年7月
-
New species and records of Leuctridae (Plecoptera) from Guangxi, China, on the basis of morphological and molecular data, with emphasis on Rhopalopsole(中国広西のホソバカワゲラ科の新種の記載:トゲホソカワゲラ属の形態学的分析と分子生物学的データに着目して)
査読
Weihai Li, Dávid Murányi, Maribet Gamboa, Ding Yang, Kozo Watanabe
Zootaxa
4243
(
1
)
165
-
176
2017年3月
-
Catchment-scale modeling of riverine species diversity using hydrological simulation: application to tests of species-genetic diversity correlation(水文シミュレーションを用いた河川種多様性の流域スケールモデリング:種多様性と遺伝的多様性の相関分析への応用)
査読
Kei Nukazawa, So Kazama, Kozo Watanabe
ECOHYDROLOGY
10
(
1
)
e1778
2017年1月
-
次世代シーケンス解析による瀬切れ河川の水生昆虫複数種を対象とした流域内交流パターンの網羅的評価
査読
八重樫咲子, 泉昴佑, 三宅洋, 渡辺幸三
土木学会論文集G(環境)
72
(
7
)
III_115
-
III_122
2016年12月
-
メタバーコーディングを活用した排砂バイパスダム上下流間の河川底生動物の群集構造の評価
査読
渡辺幸三, 近藤俊介, 泉昂佑, 八重樫咲子
土木学会論文集G(環境)
72
(
7
)
III_489
-
III_496
2016年12月
-
Comparative assessment of primary and secondary infection risks in a norovirus outbreak using a household model simulation.(世帯ベースモデルシミュレーションを用いたノロウイルス流行期における一次感染と二次感染リスクの比較評価)
査読
国際誌
Fuminari Miura, Toru Watanabe, Kozo Watanabe, Kazuhiko Takemoto, Kensuke Fukushi
Journal of environmental sciences (China)
50
13
-
20
2016年12月
-
Spatial analysis of wing geometry in dengue vector mosquito, aedes aegypti (L.) (diptera: Culicidae), populations in metropolitan Manila, Philippines(フィリピン・メトロマニらにおけるデング熱ベクターのネッタイシマカ集団の翅形状の空間的変異)
査読
Thaddeus M. Carvajal, Lara Fides T. Hernandez, Howell T. Ho, Menard G. Cuenca, Biancamarie C. Orantia, Camille R. Estrada, Katherine M. Viacrusis, Divina M. Amalin, Kozo Watanabe
Journal of Vector Borne Diseases
53
(
2
)
127
-
135
2016年6月
-
複数の健康イベントに気候変動が及ぼす影響の解明・予測に向けた環境データ活用の試み
渡辺 知保, 門司 和彦, 福士 謙介, 渡部 徹, 片山 浩之, 渡辺 幸三, 安本 晋也, 柴崎 亮介, 小池 俊雄
日本衛生学雑誌
71
(
Suppl.
)
S200
-
S200
2016年5月
-
Identification of Outlier Loci Responding to Anthropogenic and Natural Selection Pressure in Stream Insects Based on a Self-Organizing Map(自己組織化マップを使った河川性昆虫の人為および自然由来の環境選択に受ける外れ遺伝子座の同定)
査読
Bin Li, Kozo Watanabe, Dong-Hwan Kim, Sang-Bin Lee, Muyoung Heo, Heui-Soo Kim, Tae-Soo Chon
WATER
8
(
5
)
2016年5月
-
Characterization of Genes Coding for Histone H3, 18S rRNA, and Cytochrome oxidase subunit I of East Asian Mayflies (Ephemeroptera)(東アジア産カゲロウのHistone H3, 18S rRNA, およびCytochrome oxidase subunit I領域における遺伝子コードの特性)
査読
Kei Wakimura, Yasuhiro Takemon, Atsushi Takayanagi, Shin-ichi Ishiwata, Kozo Watanabe, Kazumi Tanida, Nobuyoshi Shimizu, Mikio Kato
DNA Barcodes
4
1
-
25
2016年4月
-
水文モデルと底生動物の生息場モデルを用いた河川健全度パターンの評価
査読
糠澤 桂, 風間 聡, 渡辺 幸三
水工学論文集 Annual journal of Hydraulic Engineering, JSCE
60
Ⅰ_433
-
438
2016年3月
-
A hydrothermal simulation approach to modelling spatial patterns of adaptive genetic variation in four stream insects(水生昆虫4種の適応的な遺伝的多様性の空間変動のモデリングへの水文温度シミュレーションアプローチ)
査読
Kei Nukazawa, So Kazama, Kozo Watanabe
JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY
42
(
1
)
103
-
113
2015年1月
-
ダムおよび瀬切れによる河川分断化がエルモンヒラタカゲロウの地域間交流に及ぼす影響の遺伝的評価
八重樫 咲子, 不破 直人, 山崎 久美子, 三宅 洋, 渡辺 幸三
土木学会論文集G(環境)
71
(
7
)
III_115
-
III_121
2015年
-
Effects on river macroinvertebrate communities of tsunami propagation after the 2011 Great East Japan Earthquake(東日本大震災で発生した津波遡上波が河川大型無脊椎動物群集に及ぼした影響)
査読
Kozo Watanabe, Sakiko Yaegashi, Hiro Tomozawa, Shunichi Koshimura, Tatsuo Omura
FRESHWATER BIOLOGY
59
(
7
)
1474
-
1483
2014年7月
-
Fine-scale dispersal in a stream caddisfly inferred from spatial autocorrelation of microsatellite markers(マイクロサテライトマーカーの自己相関分析により推定された微小空間スケールにおける河川性トビケラの移動分散)
査読
Sakiko Yaegashi, Kozo Watanabe, Michael T. Monaghan, Tatsuo Omura
FRESHWATER SCIENCE
33
(
1
)
172
-
180
2014年3月
-
水生生物の生息場適性度と遺伝的多様性の関係
査読
糠澤 桂, 風間 聡, 高瀬 陽彦, 渡辺 幸三
土木学会論文集B1(水工学)
70
(
4
)
I_1405
-
I_1410
2014年3月
-
Adaptive genetic divergence along narrow environmental gradients in four stream insects.(水生昆虫4種が狭い環境勾配に沿って見せた適応的な遺伝的多様性)
査読
国際誌
Kozo Watanabe, So Kazama, Tatsuo Omura, Michael T Monaghan
PloS one
9
(
3
)
e93055
2014年
-
家庭内での二次感染を考慮したノロウイルス感染症伝播モデルの構築
三浦 郁修, 渡部 徹, 渡辺 幸三, 福士 謙介
土木学会論文集G(環境)
70
(
7
)
III_295
-
III_304
2014年
-
分布型水文モデルと確率密度関数を用いた底生動物の生息環境および種多様性評価
査読
高瀬 陽彦, 糠澤 桂, 風間 聡, 渡辺 幸三
土木学会論文集B1(水工学)
70
(
4
)
I_1297
-
I_1302
2014年
-
河川の水質環境および物理環境がヒゲナガカワトビケラの遺伝的多様性に与える影響
査読
八重樫咲子, 渡辺幸三, 大村達夫
環境工学研究論文集
50
III.489-III.494
2013年11月
-
Effects of predation pressure and resource use on morphological divergence in omnivorous prey fish.
査読
Scharnweber K, Watanabe K, Syväranta J, Wanke T, Monaghan MT, Mehner T
BMC evolutionary biology
13
132
2013年6月
-
ダム下流河川の流水性・止水性ハビタット間の微粒状有機物の起源の違い
高橋 真司, 竹門 康弘, 大村 達夫, 渡辺 幸三
土木学会論文集G(環境)
69
(
7
)
III_547
-
III_555
2013年
-
河川の水質環境および物理環境がヒゲナガカウトビケラの遺伝的多様性に与える影響
八重樫 咲子, 渡辺 幸三, 大村 達夫
土木学会論文集G(環境)
69
(
7
)
III_489
-
III_494
2013年
-
分布型流出・水温モデルを使用した水生昆虫の生息環境評価
高瀬 陽彦, 糠澤 桂, 風間 聡, 渡辺 幸三
土木学会論文集B1(水工学)
69
(
4
)
I_1255
-
I_1260
2013年
-
HSI種多様性に基づく流域の遺伝的多様性空間分布の予測
査読
糠澤 桂, 風間 聡, 渡辺 幸三
土木学会論文集B1(水工学)
69
(
4
)
I_1303
-
I_1308
2013年
-
河川ハビタッチ構造と水生昆虫モンカゲロウの遺伝的多様性の関係
査読
八重樫咲子, 渡辺幸三, 高橋真司, 永峯賢人, 大村達夫
環境工学研究論文集
49
III.611-III.616
2012年11月
-
高精度GPSを用いた河川ハビタット構造の定量化と底生動物の種多様性保全への活用
査読
高橋真司, 渡辺幸三, 竹門康弘, 大村達夫
応用生態工学
15
(
1
)
121
-
130
2012年7月
-
河川生物のHSI種多様性と遺伝的多様性の関係性について
糠澤 桂, 風間 聡, 渡辺 幸三
土木学会論文集G(環境)
68
(
7
)
III_603
-
III_610
2012年
-
Delineation of habitat structure in rivers using a high precision gps for conservation of species diversity of invertebrate communities
査読
Shinji Takahashi, Kozo Watanabe, Yasuhiro Takemon, Tatsuo Omura
Ecology and Civil Engineering
15
(
1
)
121
-
130
2012年
-
河川ハビタット構造と水生昆虫モンカゲロウの遺伝的多様性の関係
八重樫 咲子, 渡辺 幸三, 高橋 真司, 永峯 賢人, 大村 達夫
土木学会論文集G(環境)
68
(
7
)
III_611
-
III_616
2012年
-
マイクロサテライトマーカーを用いたヒゲナガカワトビケラの流域内および流域間移動分散の評価
査読
八重樫咲子, 渡辺幸三, 大村達夫
土木学会論文集G(環境)
67
(
7
)
III_99
-
III_106
2011年11月
-
マイクロサテライトマーカーを用いたヒゲナガカワトビケラの流域内および流域間移動分散の評価
査読
八重樫咲子, 渡辺幸三, 大村達夫
環境工学研究論文集
48
III.99-III.106
2011年11月
-
Benthic communities and genetic structure of caddisfly stenopsyche marmorata along a mountain stream fragmented by slit and unslit sabo dams
査読
K. Nukazawa, S. Kazama, K. Watanabe, J. Kang
WIT Transactions on Ecology and the Environment
146
263
-
274
2011年
-
Dispersal ability determines the genetic effects of habitat fragmentation in three species of aquatic insect
査読
Kozo Watanabe, Michael T. Monaghan, Yasuhiro Takemon, Tatsuo Omura
AQUATIC CONSERVATION-MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEMS
20
(
5
)
574
-
579
2010年7月
-
透過型・不透過型砂防ダムの存在する山地渓流における底生動物群集の種多様性
査読
糠澤桂, 風間聡, 渡辺幸三
水工学論文集(CD-ROM)
54
ROMBUNNO.215
2010年2月
-
炭素・窒素安定同位体比を用いた河畔林由来の有機物が水生昆虫群集へ与える影響について
査読
高橋真司, 五十嵐夏奈, 伊藤歩, 渡辺幸三, 相澤治郎, 大村達夫, 海田輝之
環境工学研究論文集
46
1
-
8
2009年11月
-
進化系統を考慮した河川水生昆虫ヒゲナガカワトビケラの遺伝的多様性の評価
査読
鈴木祥一, 渡辺幸三, 八重樫咲子, 大村達夫
環境工学研究論文集
46
529
-
536
2009年11月
-
Permanent Genetic Resources added to Molecular Ecology Resources database 1 January 2009-30 April 2009
査読
L. G. Abercrombie, C. M. Anderson, B. G. Baldwin, I. C. Bang, R. Beldade, G. Bernardi, A. Boubou, A. Branca, F. Bretagnolle, M. W. Bruford, A. Buonamici, R. K. Burnett, D. Canal, H. Cardenas, C. Caullet, S. Y. Chen, Y. J. Chun, C. Cossu, C. F. Crane, S. Cros-Arteil, R. Cudney-Bueno, R. Danti, J. A. Davila, G. Della Rocca, S. Dobata, L. D. Dunkle, S. Dupas, N. Faure, M. E. Ferrero, B. Fumanal, G. Gigot, I. Gonzalez, S. B. Goodwin, D. Groth, B. D. Hardesty, E. Hasegawa, E. A. Hoffman, M. L. Hou, A. F. J. Jamsari, H. J. Ji, D. H. Johnson, L. Joseph, F. Justy, E. J. Kang, B. Kaufmann, K. S. Kim, W. J. Kim, A. V. Koehler, B. Laitung, P. Latch, Y. D. Liu, M. B. Manjerovic, E. Martel, S. S. Metcalfe, J. N. Miller, J. J. Midgley, A. Migeon, A. J. Moore, W. L. Moore, V. R. F. Morris, M. Navajas, D. Navia, M. C. Neel, P. J. G. de Nova, I. Olivieri, T. Omura, A. S. Othman, J. Oudot-Canaff, D. R. Panthee, C. L. Parkinson, I. Patimah, C. A. Perez-Galindo, J. B. Pettengill, S. Pfautsch, F. Piola, J. Potti, R. Poulin, P. T. Raimondi, T. A. Rinehart, A. Ruzainah, S. K. Sarver, B. E. Scheffler, A. R. R. Schneider, J. F. Silvain, M. N. Siti Azizah, Y. P. Springer, C. N. Stewart, W. Sun, R. Tiedemann, K. Tsuji, R. N. Trigiano, G. G. Vendramin, P. A. Wadl, L. Wang, X. Wang, K. Watanabe, J. M. Waterman, W. W. Weisser, D. A. Westcott, K. R. Wiesner, X. F. Xu, S. Yaegashi, J. S. Yuan
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES
9
(
5
)
1375
-
1379
2009年9月
-
DNA多型マーカーによるヒゲナガカワトビケラの流域内移動分散パターンの評価
渡辺 幸三, 八重樫 咲子, 菊池 裕二, 竹門 康弘, 風間 聡, 大村 達夫
水環境学会誌 = Journal of Japan Society on Water Environment
32
(
5
)
253
-
258
2009年5月
-
Fine sediment deposition in a curved channel with an intake weir
査読
Yoshiyuki Shirotori, Kozo Watanabe, Keiko Udo, Akira Mano
Advances in Geosciences: Volume 11: Hydrological Science (HS)
223
-
235
2009年1月
-
FINE SEDIMENT DEPOSITION BY FLOODS ON THE UPSTREAM OF A WEIR WITH A CHANNEL BEND
査読
Yoshiyuki Shirotori, Kozo Watanabe, Keiko Udo, Akira Mano
ADVANCES IN WATER RESOURCES AND HYDRAULIC ENGINEERING, VOLS 1-6
815
-
820
2009年
-
Longitudinal patterns of genetic diversity and larval density of the riverine caddisfly Hydropsyche orientalis (Trichoptera)
査読
Kozo Watanabe, Michael T. Monaghan, Tatsuo Omura
AQUATIC SCIENCES
70
(
4
)
377
-
387
2008年12月
-
Biodilution of heavy metals in a stream macroinvertebrate food web: Evidence from stable isotope analysis
査読
Kozo Watanabe, Michael T. Monaghan, Yasuhiro Takemon, Tatsuo Omura
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
394
(
1
)
57
-
67
2008年5月
-
取水堰が河川底生動物群集に及ぼす影響
査読
渡辺幸三, 白鳥喜之, 有働恵子, 真野明, 大村達夫
水工学論文集(CD-ROM)
52
ROMBUNNO.194
2008年2月
-
宮城県中南部に生息する河川底生動物群集の種多様性の空間階層構造
査読
浜本洋, 風間聡, 渡辺幸三, 沢本正樹, 大村達夫
水工学論文集(CD-ROM)
52
ROMBUNNO.196
2008年2月
-
東日本の3水系に生息するヒゲナガカワトビケラの遺伝的多様性の空間階層構造
渡辺 幸三, 菊池 祐二, 風間 聡, 大村 達夫
水環境学会誌 = Journal of Japan Society on Water Environment
31
(
1
)
31
-
37
2008年1月
-
Trophic structure of stream macroinvertebrate communities revealed by stable isotope analysis
査読
Kozo Watanabe, Tatsuo Omura
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY
58
(
3
)
503
-
512
2008年
-
宮城県中南部のウルマーシマトビケラ地域集団の遺伝的多様性と分化
査読
渡辺幸三, 草野光, 大村達夫
環境工学研究論文集
44
83
-
92
2007年11月
-
ダム上下流の河川水生昆虫分集団間の遺伝的分化シミュレーション
査読
菊池祐二, 渡辺幸三, 風間聡, 大村達夫, 沢本正樹
環境工学研究論文集
44
99
-
106
2007年11月
-
ダム放流水が河川底生動物群集に及ぼす季節的影響
査読
渡辺幸三, 大村達夫
土木学会論文集 G
63
(
2
)
93
-
101
2007年7月
-
Relationship between reservoir size and genetic differentiation of the stream caddisfly Stenopsyche Marmorata
査読
Kozo Watanabe, Tatsuo Omura
BIOLOGICAL CONSERVATION
136
(
2
)
203
-
211
2007年4月
-
台風後のウルマーシマトビケラの遺伝的多様性に基づく台風前の個体群密度の推定
査読
渡辺幸三, 草野光, 大村達夫
土木学会論文集 G
63
(
3
)
186-194 (J-STAGE)
2007年
-
RAPD解析によるダム上下流の河川水生昆虫3種地域集団の遺伝的多様性の評価
渡辺 幸三, 大村 達夫
土木学会論文集
62
(
1
)
94
-
104
2006年4月
-
RAPD解析によるダム上下流の河川水生昆虫3種地域集団の遺伝的多様性の評価
渡辺 幸三, 大村 達夫
土木学会論文集 = Proceedings of JSCE
(
811
)
49
-
59
2006年2月
-
窒素・炭素安定同位体分析による河川水生昆虫群集の重金属濃縮機構の解明
渡辺 幸三, 山本 直樹, 草野 光, 大村 達夫
水環境学会誌 = Journal of Japan Society on Water Environment
28
(
12
)
737
-
744
2005年12月
-
Stochastic model for recovery prediction of macroinvertebrates following a pulse-disturbance in river
査読
K Watanabe, C Yoshimura, T Omura
ECOLOGICAL MODELLING
189
(
3-4
)
396
-
412
2005年12月
-
炭素・窒素安定同位体分析による河川底生動物群集の栄養構造の解明 : 宮城県広瀬川流域を例として
山本 直樹, 渡辺 幸三, 草野 光, 大村 達夫
水環境学会誌 = Journal of Japan Society on Water Environment
28
(
6
)
385
-
392
2005年6月
-
ヒゲナガカワトビケラ(Stenopsyche marmorata)地域集団のRAPD解析によるダム上下流間の遺伝的分化の評価
渡辺 幸三, 大村 達夫
土木学会論文集 = Proceedings of JSCE
(
790
)
49
-
58
2005年5月
-
Pulse 型の人為的インパクトを受けた河川底生動物の回復予測モデル
渡辺 幸三, 吉村 千洋, 小川原 享志, 大村 達夫
土木学会論文集 = Proceedings of JSCE
(
748
)
67
-
79
2003年11月
-
生態学的パラメータによる河川底生動物群集の動態特性の評価
渡辺 幸三, 吉村 千洋, 小川原 享志, 大村 達夫
土木学会論文集 = Proceedings of JSCE
734
(
734
)
99
-
110
2003年5月
-
RAPD法によるHydropsyche orientalis(Hydropsychidae:Trichoptera)の遺伝的多様性に基づく河川環境評価 : 宮城県名取川水系を例として
小川原 享志, 渡辺 幸三, 吉村 千洋, 大村 達夫
水環境学会誌 = Journal of Japan Society on Water Environment
26
(
4
)
223
-
229
2003年4月